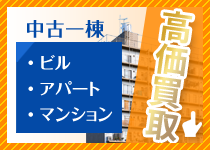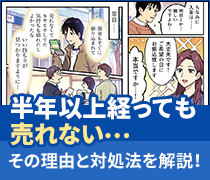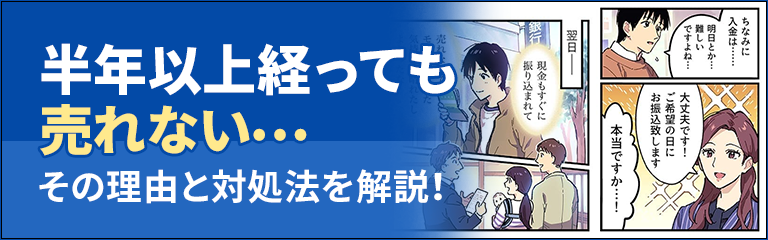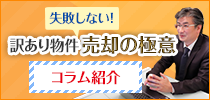活用できていない再建築不可物件、持て余している再建築不可物件は早めに売却してしまうのが得策です。一方で、再建築ができないゆえになかなか売りにくいのも実情であり、「売りたくても売れない」と困られている方も少なくありません。
この記事では再建築不可物件を売却する方法や所有し続けるリスクについてご説明します。
目次
再建築不可物件の売却方法
再建築不可物件を売却する手段としては大きく分けて「再建築可能な状態にして売却する」という方法と「再建築不可状態のまま売却する」という方法の2パターンがあります。さらに、再建築不可のまま売却する場合は、隣地所有者に売却する、仲介業者や買取業者に売却するなど、さまざまな方法があります。
せっかく物件を売るなら、なるべく利益を得たいというのが人情というもの。注意点も含めて、それぞれ詳しく見ていきましょう。
再建築可能にして売却
再建築不可物件を再建築可能な状態にすることで、相場通りの価格で売却できる、再建築不可状態よりも買い手が見つかりやすくなるといったメリットがあります。
そもそも再建築不可物件は接道義務を満たしていないがために建築許可が下りない状態の物件のことを指します。道路に接している隣地を買い取るか借りるかして合筆する、土地をセットバックして行政に道路としてみなしてもらう、但し書き規定の申請を行うなどの方法で接道義務を満たすことで、再建築可能となります。
しかしながら、これらの方法は手間と費用がかかりハードルがかなり高いです。再建築不可物件を再建築可能な状態にする方法については、「再建築不可は建て替え可能にできるが… 一筋縄ではいかない実情とは?!」で詳しくご説明しています。
再建築不可のまま売却
再建築不可物件を再建築可能な状態にすることもできないわけではありませんが、膨大な手間と費用がかかるため、あまり現実的とはいえない手段です。特に「早めに物件を売却したい」「なるべくスムーズに売却したい」とお考えでしたら、再建築不可のまま売却してしまったほうが良いかもしれません。
再建築不可物件を売る方法としては主に「隣地所有者への売却」「仲介での売却」「買取での売却」という3つの方法があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
隣地所有者への売却
増築したい、ガレージが欲しい、庭を造りたいと隣地の所有者が考えている場合は、再建築不可物件を買い取ってくれる可能性があります。物件を直接売却すれば、仲介手数料などの費用を抑えることができて、不動産業者を探したり買い手を募ったりといった手間も不要です。再建築不可物件を売却する際には、まずは隣地の所有者に声をかけてみるのもいいかもしれません。
ただし、個人間で不動産を売買する場合はトラブルが発生するリスクがあります。場合に応じて不動産の専門家や弁護士、司法書士などの法律家に相談されることをおすすめします。また、そもそも隣地の所有者が物件の購入を希望していなければ、売却することができません。
仲介での売却
仲介(ちゅうかい)は、不動産を売買する際によくとられる方法です。不動産仲介会社と媒介契約を結び、買い主を募ります。買い主が見つかったら仲介会社を通して交渉を行い、話がまとまったら売り主と買い主が不動産売買契約を締結します。
不動産売買のプロである仲介会社が手続きをサポートしてくれるので、トラブルが少ないのがメリットです。しかし一方で売買が成立した場合は仲介会社に仲介手数料を支払わなければならないため、売却によって得られる利益が目減りしてしまうというデメリットも考えられます。
また、仲介の場合は業者が物件を買い取ってくれるわけではないことに注意しましょう。物件情報を公開して購入希望者を見つける必要があります。特に再建築不可物件はなかなか買い手が見つからず、売却まで時間がかかってしまったり、そもそも売れなかったりというケースも少なくありません。
買取での売却
不動産買取業者に買い取ってもらうという手段もあります。仲介の場合は第三者に物件を売却しますが、買取の場合は業者が買い主となるため、スムーズに売却できる可能性があり、仲介手数料も必要ありません。相手は不動産の専門家なので、トラブルが発生するリスクも低いです。
ただし、再建築不可物件を扱っている業者は少数であり、業者探しが難しい点には注意しましょう。再建築不可物件はどうしても市場価値が低くなってしまうため、買取を断られてしまうケースも少なくありません。また、ごく一部ですが足元を見て不当に安く買い叩いたり、契約不適合責任を盾にして値下げや金銭の支払いを要求したりする悪徳業者も散見されますので、注意しましょう。
【注意】契約不適合責任
不動産を売買する際には、「契約不適合責任」が生じることにも留意しておきましょう。契約不適合責任とは、引き渡したものがあらかじめ契約書で取り決めた種類や数量、品質などを満たしていない場合に、売り主が買い主に対して負う責任です。仮に物件に瑕疵(不具合)があった場合、買い主から減額請求や契約解除請求、損害賠償請求などがなされるおそれもあります。
再建築不可物件は築年数が古いケースがほとんどです。仲介や直接取引で買い主に引き渡した後に雨漏りやシロアリ被害などが見つかって契約不適合責任が問われるケースも数多くあります。前述のとおり買取業者に売却した場合、契約不適合責任を理由に不当な要求がなされるリスクも0ではありません。
特に買取で売却する際には、契約不適合責任を免責としている業者を選びましょう。
【2025年1月最新】建築基準法の4号特例の縮小に注意!
2025年3月までの建築基準法では、建築物を規模別に1号から4号までに分類しています。
大まかには、1号は大規模特殊建築物、2号は3階建て以上の木造建築物、3号は2階建て以上かつ木造以外の建築物、4号はその他(小規模建築物)です。
建築基準法の4号特例縮小について、この章では「4号特例に該当する建物」や「4号特例の縮小で、再建築不可物件をお持ちの場合は具体的にどんなことに気をつければいいか」について、わかりやすく解説します。
建築基準法「4号特例」とは?
建築基準法において「4号特例」とは建築士が設計を行う際、規定で決められた建物に対して、構造関係規定などの審査が省略される特例制度のことです。 2025年3月まで、4号特例の対象となっていたのは、
- 木造二階建て
- 木造平屋建て
などの小規模建築物です。再建築不可物件に多くみられる形状の建物といえます。
どう変わる?4号特例の実質廃止と言われる訳とは
4号特例の縮小によって、建築基準法における「4号」は新2号、新3号として分類され、実質的に廃止されます。
大規模リフォーム時の建築確認などが基本的には必須とされ、再建築不可物件はさらに売れにくくなります。
4号特例に代わる新2号建築物・新3号建築物
今回の特例縮小の対象になるのは、これまで4号特例が適用されていた建物です。
これらは新2号建築物と新3号建築物として分類されます。
このうち、新2号建築物(木造2階建てや延べ面積200㎡以上の平屋)を所有されている場合は、リフォームを行う際に建築確認申請が必要になります。
ただ、木造平屋建てのうち延べ面積200㎡以下のもの(新たに3号として分類)については引き続き、大規模リフォーム時の建築確認は不要です。
再建築不可物件をお持ちの場合は、新2号・新3号のどちらに該当するか確認しましょう。
新2号建築物と新3号建築物、どちらにに該当する?チェックボックス
省エネ基準への適合が義務
省エネ基準への適合が義務付けられる点も、今回の特例縮小における重要な変更点のひとつです。
これまで、申請時に必要とされていた「確認申請書・図書」に加えて新2号建築物では、
構造関連規定等の図書(構造関係の図面・計算書)、省エネ関連の図書(省エネ適合性などの判定済通知書等)の提出が新たに義務付けられます。
なお、新3号建築物に関しては、特例縮小後も従来通りの書類の提出義務が維持される形となっています。
安全性や環境負荷軽減などを念頭に置いた、建築の質の向上を目指した今回の特例縮小。基準適合の確認が厳格化され、提出書類も従来より、しっかりした内容のものが求められることになるでしょう。
4号特例の縮小が再建築不可物件に与える影響
これから増改築を!とお考えの皆様にとって、4号特例縮小による影響は大きいといえます。
今回の特例縮小では建築確認・検査が必要となる建物が大幅に増え、審査省略制度も適用されにくくなります。再建築不可物件の売却を考える場合は、頭の痛いところです。
再建築不可物件の買取・売却の難化
今回の制度縮小を受け、小規模な建物の売却・買取が難しくなる状況を想定する必要があるでしょう。
小規模建築は接道義務等の観点から、再建築不可となるケースがよくあります。
再建築不可物件は今後、輪をかけて売りにくくなります。建物を残したまま売ることができなければ、上物を壊して更地にするといった手間や費用が必要になるでしょう。
再建築不可物件に対応する買取・仲介業者が減少
こうした状況を受け、買取業者や仲介業者も再建築不可物件に対する評価のハードルが上がるでしょう。
買い取ってもリフォームできない、仲介しようにも買い手への説明が難しいなどと、取引に困難が予想されるからです。
再建築不可物件をお持ちの場合は早めに、事情に精通した業者などへ相談しましょう。
空き家問題がさらに深刻化
主に小規模住宅に適用されていた特例が縮小(実質的廃止)されることで、もともと売却や買取が難しい再建築不可物件等の所有者のなかには「リフォームは面倒」「更地にすると固定資産税が上がる」などと考える人が現れ、建物が放置され大量の空き家が発生することも想像にかたくないでしょう。
そうなる前に、こうした物件をお持ちの方はできるだけ早めに解決策を見出したいところです。
再建築不可物件の相場価格
 再建築不可物件はどうしても周辺の一般的な物件と比較すると買取価格が下がってしまい、相場は良くて7割程度、多くの場合半値くらいにしかなりません。
再建築不可物件はどうしても周辺の一般的な物件と比較すると買取価格が下がってしまい、相場は良くて7割程度、多くの場合半値くらいにしかなりません。
再建築不可物件が安値でしか売れない要因としてまず挙げられるのが、自由度の低さです。再建築はもちろん、増築や改築も認められないため、資産としての価値が低く見られてしまいます。加えて築年数が古いのも要因です。
もちろん、物件の立地や状態にもよりますが、まず通常の価格では売れないと思っておいたほうが無難です。再建築不可物件の買取相場や査定基準、買取価格が低い理由については、「再建築不可の買取相場はどれくらい低い? ~できるだけ高く売るなら~」で詳しくご説明しています。
再建築不可物件を持ち続けるリスク
 再建築不可物件を現状のまま所有し続けるという選択肢もあるのですが、さまざまなリスクが伴います。特に使用していない場合は、以下のようなことも考慮した上で、持ち続けるか?売却するか?を検討してみましょう。
再建築不可物件を現状のまま所有し続けるという選択肢もあるのですが、さまざまなリスクが伴います。特に使用していない場合は、以下のようなことも考慮した上で、持ち続けるか?売却するか?を検討してみましょう。
税金
不動産には固定資産税と都市計画税という税金がかかります。毎年1月1日時点で不動産を所有している人が対象で、建物や土地の価値によって税額が決まります。当然のことながら、再建築不可物件を所有している限り、これらの税金を支払い続けなければなりません。
特に注意していただきたいのは再建築不可物件を解体して更地にしたり、駐車場などほかの用途に利用したりといったことを検討されている方です。住宅の場合は減税措置が適用されていますが、解体してしまえば対象外になってしまうため、税額が大幅に跳ね上がる可能性があります。
不法投棄・不法侵入
再建築不可物件に住んでおらず空き家状態になっている場合は特に要注意です。不法投棄や不法侵入などの犯罪の温床になるリスクがあります。
不法投棄がされれば地域の美観を損ねる、近隣から苦情を言われる、放火の被害に遭う、土壌などの環境が汚染されるなどのさまざまなトラブルが発生する危険性が高いです。
空き家をホームレスが寝床にしたり、非行少年や犯罪者集団、反社会的勢力がアジトとして出入りしたりするケースもよくあることです。地域の治安が悪化する、建物が破壊される、人的な被害が生じるといったトラブルに発展するおそれも、想像に難くないでしょう。
物件価値の下落
建物は所有し続ければし続けるほど、価値が低くなってしまいます。ただでさえ資産価値が低く見られがちな再建築不可物件を放置しておくことで、まずまず売りにくい状況に陥ってしまうでしょう。また、建物の老朽化が進めば修繕費や維持費も嵩みます。費用や手間をかけたのに売れないとなると、目も当てられません。
今この瞬間も劣化は進んでいます。売却を考えられているのであれば、なるべく早く動き出しましょう。
ただ再建築不可物件の売却は難しい
 ここまで再建築不可物件の売却方法や所有し続けるリスクについてご紹介してきました。税金や維持費がかかり続ける一方で資産価値は下落しつづけ、トラブルが発生するリスクも高いことから、物件を持て余しているのであれば、早めに売却されることを強くおすすめします。
ここまで再建築不可物件の売却方法や所有し続けるリスクについてご紹介してきました。税金や維持費がかかり続ける一方で資産価値は下落しつづけ、トラブルが発生するリスクも高いことから、物件を持て余しているのであれば、早めに売却されることを強くおすすめします。
しかし、以下のような理由から再建築不可物件の売却は非常にハードルが高いのも事実です。
再建築できない
再建築不可物件が売れない一番大きな要因はやはり再建築ができないことです。先ほどもご説明したとおり、再建築不可物件は基本、新築や増築、改築が認められていません。再建築不可物件の購入者は建物をそのまま使い続けるか、再建築可能な状態にして建て替えやリフォーム工事を行うか、更地にするしかありません。しかも、更地にしてしまえば建物を建てることができなくなってしまいます。
再建築不可物件は自由度が低く、再建築できる状態にもっていくには非常に手間がかかるため、市場価値が低くなってしまうのです。
融資が下りづらい
ローンを利用して購入しづらいという買主側の事情も、再建築不可物件が売れない要因のひとつです。一般的に融資を利用する際には購入する物件を担保にしてお金を借り入れます。しかし、資産価値が低い再建築不可物件は担保として認められず、ローンの審査に通過しない可能性があるのです。
買取業者・仲介会社の「売れる売れる詐欺」に注意!
 仲介を利用する場合は、「売れる売れる詐欺」にも注意しましょう。仲介業者の中には媒介契約が欲しいがために、相場以上の査定額を提示することがあります。契約を締結して仲介を依頼したはいいものの、物件の価格が割高であるため、なかなか買い手が見つからないというケースも少なくありません。仲介業者はあくまで売り手と買い手を仲介する役割です。物件が売れなくても損はしません。売り手だけがいつまで経っても利益を得られず、税金や維持費などのコストを支払い続けることになってしまうのです。
仲介を利用する場合は、「売れる売れる詐欺」にも注意しましょう。仲介業者の中には媒介契約が欲しいがために、相場以上の査定額を提示することがあります。契約を締結して仲介を依頼したはいいものの、物件の価格が割高であるため、なかなか買い手が見つからないというケースも少なくありません。仲介業者はあくまで売り手と買い手を仲介する役割です。物件が売れなくても損はしません。売り手だけがいつまで経っても利益を得られず、税金や維持費などのコストを支払い続けることになってしまうのです。
仲介業者の担当者が再建築不可と気づかずに本来の資産価値よりも高値をつけた結果売れなくなってしまうというケースもよくあります。こうしたケースでは売却にこぎつけても、売れたあとに再建築不可と判明すれば大問題になるでしょう。
今すぐ手放すなら再建築不可物件の買取専門業者にご相談!
再建築不可物件は建て替えはもちろん、基本的にリフォームもできず、所有することでコストがかかり続けます。売却までのハードルは非常に高いです。所有し続けることも売ることもできずに困っているのであれば、買取業者に相談しましょう。手を焼いていた再建築不可物件もスムーズに売却できる可能性があります。
訳あり物件買取センターは再建築不可物件も含めた訳あり物件の買取専門業者です。創業34年以上の物件活用ノウハウと充実した販路で、再建築不可物件であっても高値で買取らせていただきます。最短即日の入金も可能。契約不適合責任は免責なので、トラブルが発生するリスクもありません。
再建築不可物件でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
再建築不可の買取のご相談は訳あり物件買取相談所へ!
訳あり物件買取相談所では業界歴30年以上の豊富な経験で、多くの再建築不可能物件を買取してきた実績があります。事情に寄り添い、買取だけでなく、丁寧・安心のサポートをお約束いたします。
複雑な事情がからむ再建築不可物件もプロの視点で、最適な解決策を提示します。ご相談だけでも大歓迎ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相談は無料です。専門のスタッフが心を込めて、対応いたします。
宮野 啓一
株式会社ティー・エム・プランニング 代表取締役
| 国内 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:150件 |
| 国内 | 訳あり物件売買取引件数:1150件 |
| 海外 | 不動産トラブルの訴訟・裁判解決件数:30件 |
※宮野個人の実績件数

経歴
1964年、東京(六本木)生まれ。叔父・叔母がヨーロッパで多くの受賞歴を持つ一級建築士で、幼少期より不動産や建築が身近なものとして育つ。
日本大学卒業後、カリフォルニア州立大学アーバイン校(UCI)に入学。帰国後は大手ビルオーナー会社に就職し、不動産売買を行う。
平成3年、不動産業者免許を取得し、株式会社ティー・エム・プランニングを設立。同時期より第二東京弁護士会の (故)田宮 甫先生に師事し20年以上に渡り民法・民事執行法を学ぶ。
現在まで30年以上、「事件もの」「訴訟絡み」のいわゆる「訳あり物件」のトラブル解決・売買の実績を積む。
またバブル崩壊後の不良債権処理に伴う不動産トラブルについて、国内・海外大手企業のアドバイザーも兼務し数多くの事案を解決。
日本だけでなくアメリカや中国の訳あり物件のトラブル解決・売買にも実績があり、国内・海外の不動産トラブル解決に精通。米国には不動産投資会社を持ち、ハワイ(ワイキキ・アラモアナエリア)・ロサンゼルス(ハリウッド・ビバリーヒルズ・サンタモニカエリア)を中心に事業を行う。
再建築不可物件に関する
疑問はここで解決!


- 再建築不可物件とは?後悔しないために知るべき基本情報
- 接道義務違反で再建築不可に!接道義務とは?どんな問題が?
- 市街化調整区域だと再建築不可?特徴や売却・再建築可能条件まで網羅解説
- 再建築不可物件の条件と判断基準をこの道30年のプロが徹底解説
- 再建築不可物件の調べ方とは?確認方法や必要書類などプロが網羅解説!
- 【弁護士も頼る専門家が解説】仲介を検討中の方!契約不適合責任に要注意!
- 【弁護士も頼る専門家が解説】買取業者へ売却!契約不適合責任に要注意!
- 再建築不可でもローンは組める ~否定されすぎな再建築不可物件購入~
- 再建築不可物件にフラット35は使える?所有者視点で他の方法も考察
- 再建築不可物件の固定資産税の全貌 ~払いすぎなケースは少なくない~
- 相続したら再建築不可物件だった!?
- どうする?!再建築不可を相続した時の対処法
- ライフライン問題のある再建築不可物件の買取出来ない?
- 崖条例で再建築不可?
- 再建築不可物件が倒壊したら再建築できない!?再建築不可物件のリスク
- 連棟式建物は再建築不可?建替え可能にする方法や他の対処方法を解説




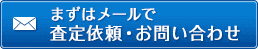
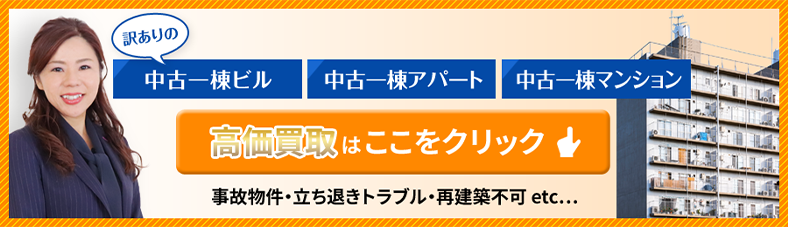

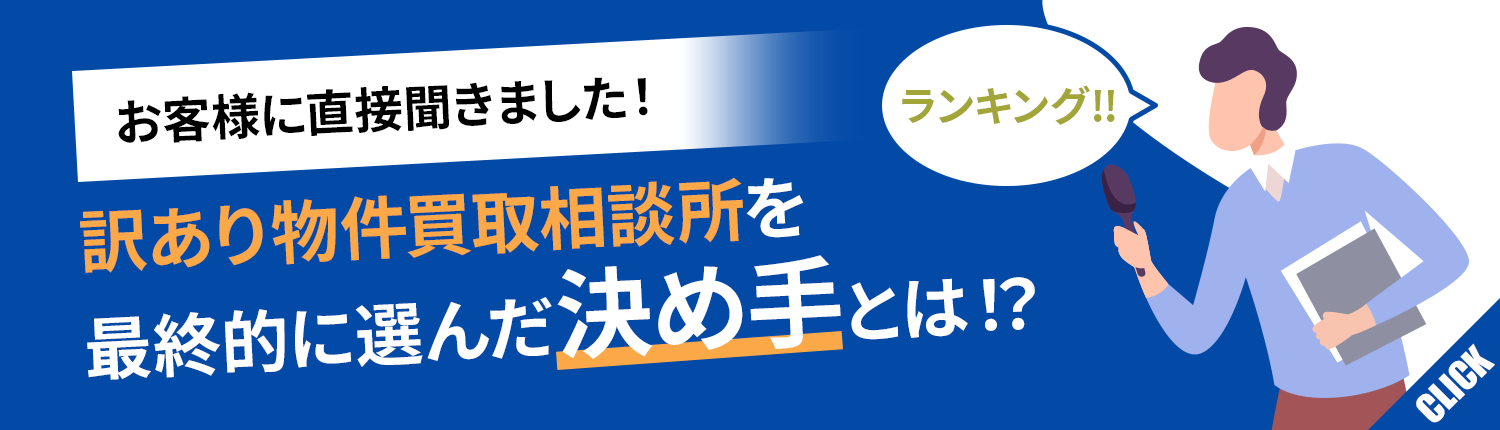
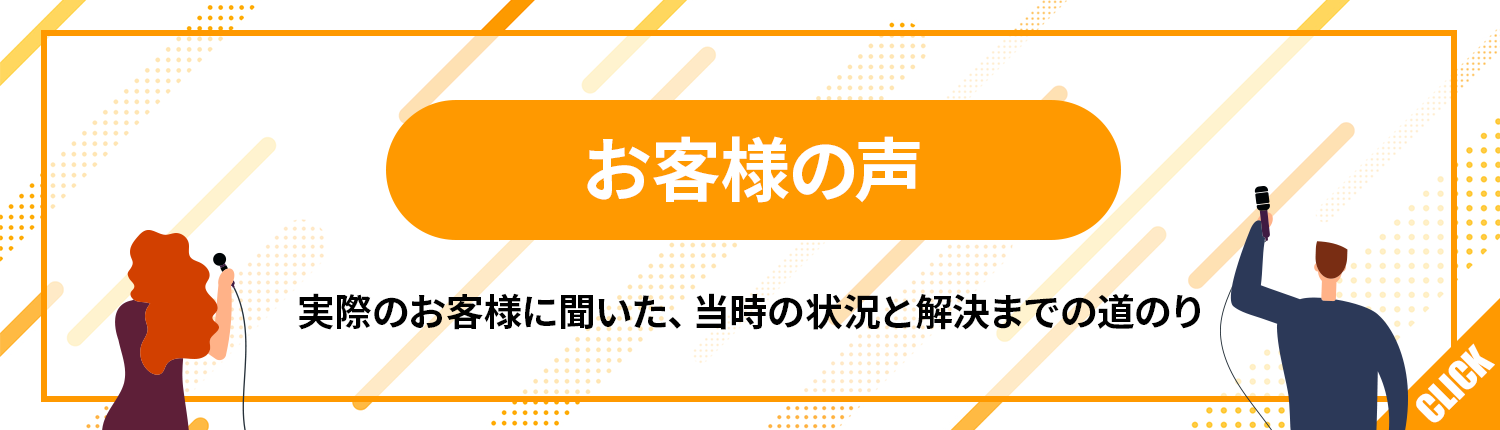
 会社概要
会社概要 お問い合わせ
お問い合わせ